週末に YouTube をザッピングしていると、データで教育改革!教育経済学者・中室牧子 という番組を見つけて面白そうなので見てみました。とても勉強になるいい番組だったので、さっそく中室牧子さんの著書「学力の経済学」という本を買って読んでみました。これが本当にいい本で、教育という極めて定性的である分野に対して、経済学や統計学、社会学の研究結果というデータを大量に投げ込んで来てさまざまな問いに答えていくという内容でした。まずは前半の第二章の途中までをまとめてみます。
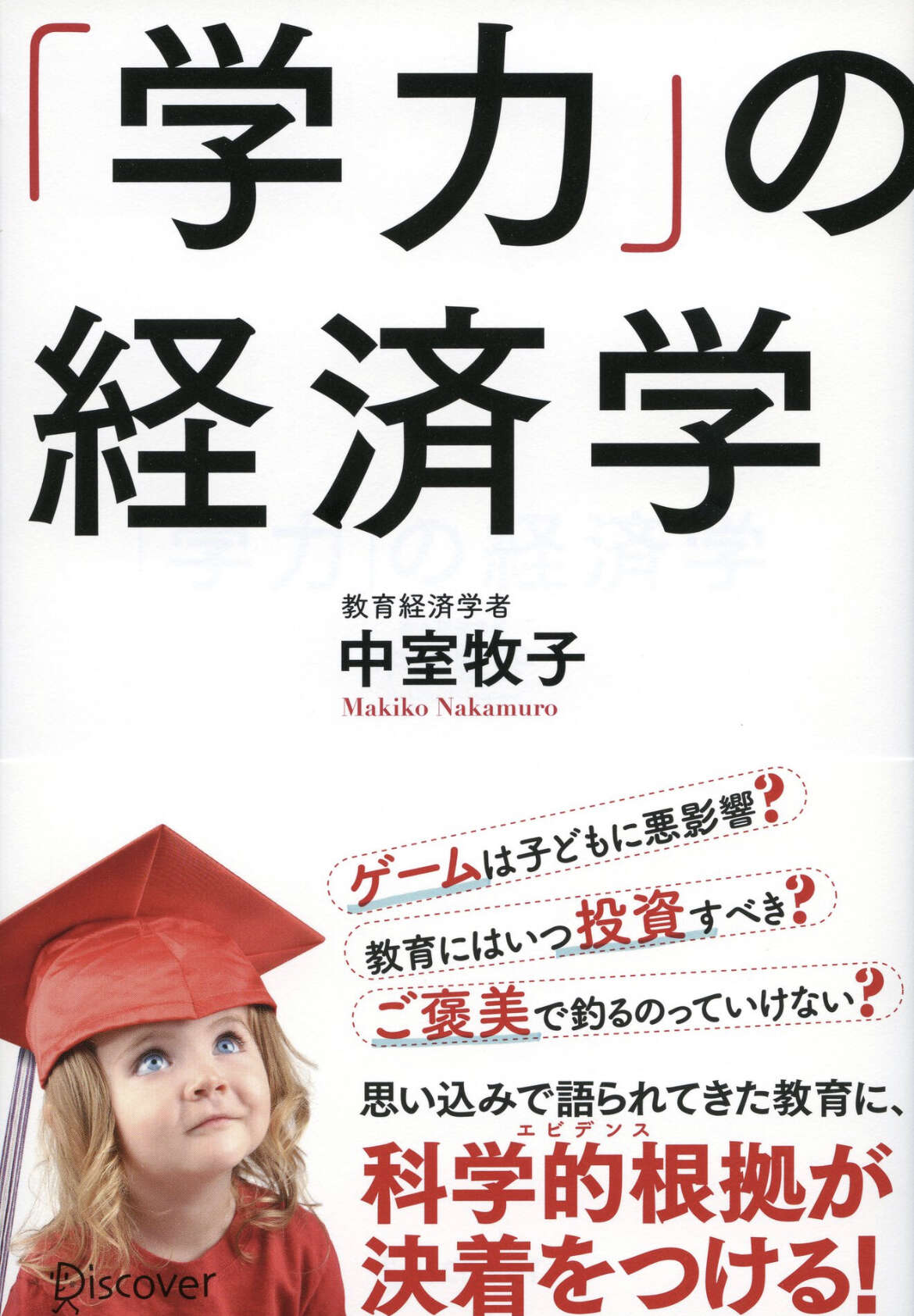
日本国民一億総教育評論家
著者の中室牧子さんという方は教育経済学者とのことです。教育経済学という分野は初めて聞きましたが、教育を経済学の論理や手法を用いて分析する応用経済学の一分野だそうです。
教育の専門家というと、「元教員でこれまで卒業生〇万人」とか、「夜の非行少年少女をこれまで〇人助けたすごい人」とか、自身の経験を専門にしている人がよくメディアなどでも出てきますが、中室さんが信じるものは一貫してデータのみ。
経験主義に対する皮肉のようなメッセージからこの本は始まります。
教育評論家や子育ての専門家がする主張の多くは、彼らの教育者としての個人的な経験に基づいているため、科学的な根拠がなく、それゆえに「なぜその主張が正しいのか」という説明が十分になされていない
つまり「自分の経験上そうだ」という論証しかできていないのに、あたかもそれが一般的に正しいかのように語ること、そのような態度に対する反論というわけです。中室さんは「経験」などではなく、世界中の膨大な論文で提示されてきた専門家にとってのコモンセンス(=当たり前・常識)とされている科学的な事実を紹介していきます。
教育経済学者の私が信頼を寄せるのは、たった一人の個人の体験記ではありません。個人の体験を大量に観察することによって見出される規則性なのです。
第一章の冒頭は、「統計学が最強の学問である」の著者の引用から始まります。最高です🤣
自分が病気になったときに、まず長生きしているだけの老人に長寿の秘訣を聞きに行く人はいないのに、子どもの成績に悩む親が、子どもを全員東大に入れた老婆の体験記を買う、という現象が起こるのは奇妙な事態だとは思わないだろうか
実はアメリカでは、教育を科学するという態度が20年ほど前から浸透しており、「落ちこぼれ防止法」という法律では、「科学的根拠に基づく」という言葉が111回も使われていて、予算要求のシーンでも、教育政策の科学的な根拠を立証しなければならなくなっているそうです。さすがです。
因果関係と相関関係
まず、この本を読み進める上での前提となる知識を学ぶところから始まります。
経済学者だけでなく、多くの科学者、学問を行なっている人にとって因果関係と相関関係が全く異なることは常識ですが、一般の人にはあまり知られていません。因果関係と相関関係の話で有名な話に「アイスクリームの売上が伸びると、水難事故が増える」という話があります。グラフにするとこうなります。
当たり前ですが、アイスクリームの売上が伸びているのは夏だからであり、水難事故が増えているのも夏で海に入る人が増えているからであり、アイスクリームと水難事故は原因と結果の関係にはありません。わかりやすくいえば、アイスクリームを法律で禁止しても水難事故は減りません。このような関係を相関関係といいます。このような簡単な例であれば全員「当たり前じゃん!」と思うでしょう。
では、
たくさん家で読書をする子供は、学力が高い
という仮説はいかがでしょう?パッと因果関係か相関関係かわかりますか?
もちろん因果関係であり、本をたくさん読むという行為が学力を上げていると考えてることもできます。そう信じている親は多そうです。
一方で、本をたくさん買い与える家庭というのは親の経済力が高く、親の経済力が高ければ読書以外にもさまざまな教育の機会を与えているから学力が高い、つまり「親の経済力」というのが原因であり「読書の回数」と「学力の向上」は相関関係(前述のアイスクリームと水難事故の関係)であるという仮説もあります。
「何かが何かの原因である」ということ(=因果関係)を証明することは大変難しいことなのです。科学というのはこれらの難題に対して、特に教育の場合はすぐに結論を出せないため数十年間という追跡調査を膨大な人数に対して行う、気の遠くなるような作業を積み重ねています。
どこかの誰かの成功体験や主観に基づく逸話ではなく、科学的根拠に基づく教育を。経済学者は、そう提案しているのです。
Q: 子供をご褒美で釣っていいのか?
まず1つ目の疑問がこれです。これについて、アメリカで94億円を使い、約250校、小学2年生から中学3年生までの約36,000人もの子どもが参加したご褒美が学力に与える影響を調査した大規模な実験があります。
⚖️ 実験内容
- 子供に対して、「行動」と「結果」に対してご褒美を与えてみた
- 「行動」に対するご褒美とは、宿題をちゃんとする、授業にちゃんと出席するなど
- 「結果」に対するご褒美とは、通知表のスコアーやテストの点数など
⭐️ 結果
- ご褒美の種類に関わらず、子供の学習意欲は向上した
- 「行動」に対するご褒美を与えられたグループは、学力テストの結果が向上した
- 「結果」に対するご褒美を与えられたグループは、学力テストの結果がまったく向上しなかった。ただし例外として、学習を見てくれる先輩や指導者がいる場合は、アウトプットに対するご褒美を与えられたグループも学力テストの結果が向上した
どうやら、インプット(努力)に対するご褒美を与える行為には意味がありそうです。
次に、ご褒美が子供の「勉強が楽しい」という感覚を損なわないか?ということが気になります。これも実験があります。結論から言うと「インセンティブを与えたグループも、与えなかったグループも、その後の学習に対するインセンティブ(勉強って楽しいと思う気持ち)に差はなかった」そうです。
では、ご褒美はどんな種類のものがいいのでしょうか?実験の結果では、小学生ではお金よりも400円ほどの安物トロフィーのほうが効果的であり、中学生以上になると金銭的なご褒美が有効であるということがわかっています。
どれも個人の経験ではなく、数万人規模の実験から出てきたデータから導かれた結論です。まとめるとこのようになります。
💡結論 ▶︎ 学習に対してご褒美(インセンティブ)を与えることは、ご褒美の対象を間違えなければ有益であるように思える ▶︎ ご褒美を与えても勉強に対する内的動機(勉強が楽しいと思える気持ち)には変化は生まれない ▶︎ ご褒美は小学生以下では金銭的価値が大きくなくても、大きなトロフィーのような自尊心が生まれるもののほうが効果が高い
Q: 自己肯定感(自尊心)は大切?
最近、子供の自己肯定感を養うことが重要という話があります。「あなたはやればできる」「〇〇ちゃんはすごいね!」と褒めてあげて自分に自信を持たせることが大切と言う考え方です。
データによると、日本の自己肯定感(自尊心)は世界に比べるとかなり低く、また年齢が上がるごとに低下していくこともわかっているそうです。
Q: 7200人の中高生に対して「自分はダメな人間だ」という質問をしたときに「とてもそう思う」「まあそう思う」と答えた生徒の割合は? 🇨🇳中国 12% 🇺🇸米国 22% 🇰🇷韓国 45% 🇯🇵日本 65%
いくつかの研究では、自尊心が高いと
- 学習意欲や学力が高い
- 未成年の喫煙や飲酒などが少ない
- 大人になってからの勤務成績、幸福感、健康状態が良好
という傾向が示されたそうです。
そうなると当然、学校や家庭で自尊心を高めていこうという話になります。そして今から35年近く前の1986年以降に、アメリカのカリフォルニア州で大規模な研究プロジェクトが行われました。当然、「自尊心」と「学力」には強い因果関係があるであろうという仮説がおかれました。
しかし実際に調査をおこなってみると、なんと驚くことに、バラバラに行われた3つの研究のすべてで、自尊心と学力の関係には因果関係はなく、ただの相関関係であることがわかりました。
⚖️ 実験内容
- 大学の自分の授業の履修者のうち、最初の試験で成績の悪かった生徒をランダムに2つに分類
- 1つのグループにだけ毎週宿題に関する連絡とともに「あなたはやればできる!」といった自尊心を高めるメッセージを送る
⭐️ 結果
- 最初の試験で平均よりやや下の生徒は特に差は生まれなかった
- 最初の試験で成績が下位の生徒は、むしろ自尊心を高めるメッセージを送ることで成績が下がった
著者はこのように述べています。
悪い成績を取った学生に対して自尊心を高めるような介入を行うと、悪い成績を取ったという事実を反省する機会を奪うだけでなく、自分に対して根拠のない自信を持った人にしてしまう
また、詳しい研究により、因果関係はないどころか、逆であることがわかったと言うのです。つまり、「自尊心が高い」から「学力が高い」のではなく、実は逆で「学力が高い」から「自尊心が高い」という結果であったということです。
The modest correlations between self-esteem and school performance do not indicate that high self-esteem leads to good performance. Instead, high self-esteem is partly the result of good school performance. Efforts to boost the self-esteem of pupils have not been shown to improve academic performance and may sometimes be counterproductive. 自尊心と学校の成績の緩やかな相関は、自尊心の高さが学校の成績の良さにつながることを示すものではありません。むしろ、高い自尊心は良い学校の成績の結果の一部であると言えます。学生の自尊心を高めるための努力が学校の成績を向上させるという事実は示されておらず、時に逆効果になることもあります。(Translated by Shoho) Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?
自尊心と学力には相関はあるが、因果関係はない、つまりアイスクリームの売上と水難事故の件数の関係ということになります。
では、自尊心を高めるような行動はしても意味がない(しないほうがいい)のでしょうか?問題はその「褒め方」にありました。
1998年にコロンビア大学のグループが10歳から12歳の公立小学校の児童に対して行った別の実験では、「褒める」ということと「学力」の因果関係がついに示されることになります。
⚖️ 実験内容
1998年にコロンビア大学のグループが10歳から12歳の公立小学校の児童に対して行った別の実験では、「褒める」ということと「学力」の因果関係がついに示されることになります。
⚖️ 実験内容
- 1つのグループの子供には「能力」(=頭の良さや賢さ)を褒め、もう1つのグループの子供には「努力」(=行動)を褒める
- それぞれのグループにテスト(1回目)を受けてもらった。その後少し難しいテスト(2回目)を受けてもらい、そのあとに1回目と同様程度のテスト(3回目)を受けてもらった
⭐️結果
- 努力を褒められた子供は、1回目より3回目のテストで成績を伸ばした。2回目と3回目のテストでも粘り強く問題に挑戦を続き、成績が悪い原因は能力の問題ではなく、努力が足りないと考えた
- 能力を褒められた子供は、1回目より3回目のテストで成績を落とした。良い成績を取るために成績について嘘をつく傾向が高いことがわかり、成績を努力ではなく自分の才能のせいする傾向が強いことがわかった
誉めるなら、能力ではなく努力を誉めようということになります。親になると、子供が何かできるようになると結果を誉めることがよくあります。そうではなく、そこに到達するまでに子供が行った小さな努力を褒めましょうということです。
つまり、「誉める」という行動に対するベストプラクティスをまとめるとこのようになります。
💡結論 ▶︎ むやみやたらに自尊心を高めるような行動(子供を無条件に褒め称えるなど)を取ると、学力を高めるどころが落としてしまうことがある ▶︎ 子供を誉めるときは「能力」ではなく「行動」を誉める ▶︎ 子供が達成した内容(努力や行動)を適切に褒めることで、さらなる努力を引き出し、難しことでも挑戦しようとする子供に育つ可能性が高い
Q: テレビやゲームは子供に悪影響を及ぼすのか?
宗教論争のように終わらない議論があるこのテーマにも科学はある程度の解をもっています。たとえば、「テレビをみると暴力的になる」とか、「テレビをみると肥満になる」とか様々な仮説に対して、科学は比較的膨大な研究をすでにおこなっています。
まず「テレビの視聴時間と肥満」「ゲームの使用時間と問題行動」には相関があるようです。しかし我々が忘れてはならないのはそれが相関関係なのか因果関係なのか?ということです。アイスクリームの売上と水難事故の件数の話を思い出してください。
実は多くの研究で、このような結果となっています。
研究の多くは、テレビやゲーム「そのもの」が子どもたちもたらす負の因果関係は私たちが考えているほど大きくないと結論づけています。
つまり、テレビやゲームが大きな原因となり、何かよくない結果を産んでいるということはないということです。「テレビの視聴時間と肥満」「ゲームの使用時間と問題行動」には相関関係があるが、因果関係はない(アイスクリームの売上と水難事故の件数と同じ)ということになります。
それどころかテレビやゲームが学力と正の相関があるという研究もあるようです。
シカゴ大学のゲンコウ教授らは、幼少期にテレビを観ていた子どもたちは学力が高いと結論づけているほか、米国で行われた別の研究では、幼少期に「セサミストリート」などの教育番組を観て育った子どもたちは、就学後の学力が高かったことを示すものもあるのです。
参考
- Preschool Television Viewing and Adolescent Test Scores: Historical Evidence from the Coleman Study
- Television and the Informational and Educational Needs of Children
ハーバード大学のクトナー教授らは、中学生を対象にした大規模な研究によって、ゲームが必ずしも有害ではないことを明らかにしています。それどころか、17歳以上の子どもが対象になるようなロールプレイングなどの複雑なゲームは、子どものストレス発散につながり、創造性や忍耐力を培うのにむしろよい影響があるとさえ述べています。
参考
では、ゲームやテレビと学習時間はどうでしょう?著者は次のように結論づけています。
たしかにテレビやゲームと、子どもの学習時間の間には負の因果関係があることが示されています。この意味では、テレビやゲームをやめさせれば、子どもの学習時間は増えるというのは間違いではないのです。しかし、問題はその大きさです。残念ながら、1時間テレビやゲームをやめさせたとしても、男子については最大1.86分、女子については最大2.70分、学習時間が増加するにすぎないことが明らかになりました。
つまり、確かにテレビやゲームをやめさせれば学習時間は多少増えるが、1時間テレビをやめさせても、子供は机に向かって勉強することはほぼないと言うことです。
ここまで読むと、テレビもゲームも無限に見せていいように思いますが、そうではないようです。著者によると、テレビやゲームの時間が長くなりすぎると、具体的には1日2時間を超えてくると、子供の発育や学習時間への負の影響が飛躍的に大きくなるそうです。
参考
- More Time Spent on Television and Video Games, Less Time Spent Studying?
- Are Television and Video Games Really Harmful for Kids? Empirical evidence from the Longitudinal Survey of Babies in the 21st Century
つまり、このような結論になります。
💡結論 ▶︎ 1日1時間程度テレビを見たり、ゲームをしたりすることは問題ない ▶︎ むしろテレビやゲームがプラスに働くという研究もある ▶︎ 一方で、1日2時間を超えてくると、子どもの発育や学習時間に負の影響が一気に大きくなるので注意が必要
Q: 友達が子どもに与える影響は?
友達や周囲から受ける影響のことを、良いものも悪いものも「ピア・エフェクト」といいます。子供が友達からどのような影響を受けるのか?が紹介されています。
同じクラスや子供たちの「平均的な学力」から受ける影響は?
クラスの周りに賢い子がたくさんいるとどうなるのか?ということです。このようなことがわかっているようです。
▶︎ 学力の高い友達の中にいると、そのクラスでもともと学力が高かった子供のみ自分の学力にも良い影響がある ▶︎ しかしながら、中間層やもともと学力の低い子どもたちは、なんら影響を受けない ▶︎ 自分のクラスに学力の高い友人がやってくると、もともと学力が低かったこともにはマイナスの影響がある ▶︎ 学力の高い友達と一緒にいさえすれば、自分の子どもにもプラスの影響があるだろうと考えるのは間違っている
ここからわかることは、同じような学力の子どもを集めて互いに良い影響を及ぼしあう構造ができれば、ピアエフェクトがポジティブに働くということです。
新学校に行く意味はあるのか?
本書では触れられていませんが、冒頭の YouTube 動画では、ここから派生した「小さな池の大魚」効果にも触れられています。
近年では、東京23区の小学校はとんでもないことになっていて、中学受験率が50%、高いところだと70−80%になるらしく、6年生の夏休みを超えると誰も学校に来なくなるという驚くべきことになっているようです。このような新学校への進学は、学習の面で意味があるのでしょうか?
これについて著者の中室さんは「小さな池の大魚効果」で説明をしています。
「小さな池の大魚」効果とは、自分の能力よりも高い能力を持つ人々が多数を占める集団に入ると、自己肯定感が薄れ、能力が落ちてしまうということです。つまり、平均的な能力ではその学校への進学可能な学力に達していなくても偶然合格したような場合など(それはそれで当然喜ばしいことです)、自分のコミュニティにおいて自分の能力が平均よりも下位になってしまうと、能力はむしろ下がってしまうというのです。
そして、残念ながら「新学校における深海魚問題」というものもあり、一度下位に属してしまうと、そこからの浮上はかなり難しくなるという問題あるということがわかっているそうです。
一方で、たとえば第二志望の自分の学力に合った学校に進学をすると、ピア・エフェクトが働いて、学習の好循環が生まれるということになります。
つまり、どのような学校を選ぶべきか?という命題に対してピア・エフェクトの観点で答えるなら「身の丈にあった学校が一番いい」ということになります。
問題児から受ける影響
クラスの周りに問題児がいるとどんな悪い影響があるのか?ということです。このような結果がわかっています。
クラスの周りに問題児がいるとどんな悪い影響があるのか?ということです。このような結果がわかっています。
▶︎ 問題児の存在が、学級全体の学力に負の因果効果を与える ▶︎ 1人の問題児によって、他の児童が新たな問題行動を起こす確率は17%も上がる ▶︎ 偶然一緒になった友人から学力に対して受ける因果効果はほぼない ▶︎ 偶然一緒になった友人から飲酒など行動に対して受ける因果効果は大変大きい
参考
問題児の存在が、学習ではなく行動に対して強い因果効果を及ぼすことは重要なポイントです。著者はあまりに今直面している負のピアエフェクトが多い場合は、引越しが1つの選択肢であると紹介しています。
ランダムに選ばれた貧困世帯に対して、経済的に裕福な人々がクラス高級住宅地の家賃が無料になる家賃補助券を提供し、引っ越しを促しました。この結果、引っ越した家族の子どもが窃盗や暴力で逮捕される確率は、引っ越さなかった子どもよりも統計的に有意に低かったことがわかりました。負のピア・エフェクトから子供たちを救ったのです。
—
まだ半分にも達していませんが、本当に読んでいて気持ち良くなるくらい論理的で科学的でワクワクします。残りの部分も後日まとめたいと思います。